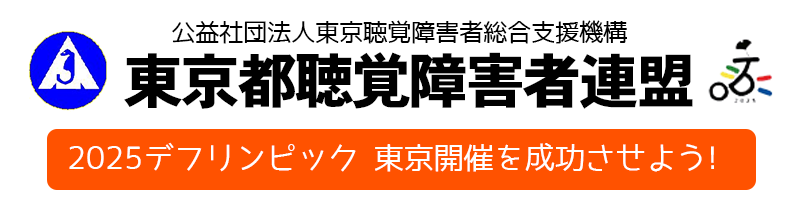2025年6月22日投票予定の東京都議会議員選挙を前に、聴覚障害者制度改革推進東京本部として、立候補予定者・各政党・会派に対して、私たちきこえない人、きこえにくい人たちの関心が高いテーマについてお考えをお尋ねするアンケートを実施しました。
以下に立候補予定者・各政党・会派にお送りした依頼文、アンケート本文、回答を掲載します。
掲載順は到着順です。回答がなかった設問は(未回答)としています。
各党の考え方を理解し、皆様が投票する際の参考としていただければ幸いです。
※当委員会が連絡先を把握できた範囲でお送りしています。
2025年6月吉日
2025年6月吉日 ○○党東京都議会議員選挙対策担当者 殿 都議会議員選挙立候補予定者・政党に対する 私たち「聴覚障害者制度改革推進東京本部」は、東京都内の聴覚障害当事者とその支援者の7団体によって構成し、聴覚障害者福祉にかかわる施策をより良いものにするべく活動しております。 記 【本文】 質問事項 2 東京都の意思疎通支援事業実施について 3 選挙時の情報保障について 4 FAX及びメールによる選挙運動について 5 公職選挙法が抱える問題について 6 その他 以上の内容について、6月12日必着で下記の連絡先にご回答をお願いいたします。メールでもFAXでも結構です。 連絡先 〒150-0011 渋谷区東1−23−3 (構成団体) 以上 |
【回答】
●都議会公明党
●田の上いくこ
●れいわ新鮮組
●東京都議会立憲民主党
●日本共産党東京都委員会
●東京・生活者ネットワーク(都議会生活者ネットワーク)
●都民ファーストの会
●東京都議会自由民主党
●都議会公明党 1. 2. 3. 4. 5. 6. |
●田の上いくこ 1. 手話言語条例につづき、情報コミュニケーションに特化して条例をつくりたいと年度をまたいで取り組んできた課題です。 中途障がいの方は、必ずしも手話になじんでいるわけではなく、障害の種類や程度に応じた意思疎通等の重要性をうたった条例です。 2. いつも会派の予算要望に取り入れてきた事項です。手話通訳者、要約筆記者派遣事業を充実させるため取り組みます。 3. 情報保証や配慮を実施します。 4. ご意見をいただきながら、国へ要望書を提出するなど検討します。 5. 上記と同じですが、現状に合った公職選挙法の改正が望まれます。国へ要望書を提出するなど検討します。 6. 手話やコミュニケーションがもっと進み、障がいがある人もない人もお互いにコミュニケーションが取れるよう必要な支援に取り組ませていただきます。 |
●れいわ新鮮組 1. 情報伝達の方法は様々であり、誰もが平等に意思疎通を図ることが出来る制度を整えることが必要です。障害は個人が努力して克服するものではなく、社会側の仕組みを変えることで障壁を取り除くことが求められます。この条例は、誰もが等しく社会参加を享受できるための一歩であると期待します。 2. 3. 4. 5. 6. |
●東京都議会立憲民主党 1. 今期、「手話言語条例」及び「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する条例」が可決・成立したことは、貴団体の運動と粘り強い働きかけの成果であると敬意を表するものです。こうした運動、働きかけがあったからこそ、私たちの呼びかけで、超党派によるWTを設置することができました。 ご質問の条例については、名称に「障害者」の文字が入りましたが、私たちは、障害者手帳 の有無にかかわらず、聞こえにくくなった高齢者など、情報コミュニケーションやアクセシビリティーに困難を抱える全ての都民等が、誰もがひとしく情報を取得、利用し、意思疎通を図ることができるよう取り組んでいきたいと考えています。 2. あります。区市町村によってサービス提供や質に大きな格差がでないよう、 専門性が高く、 緊急時にも利用ができる体制を構築するために取り組んでいく必要があると考えます。生活 に密着したサービスは、基礎自治体に提供する義務があり、利用者に不利益となるようなサービス未実施はなくしていくべきです。東京都においても、事業を実施しない自治体をカバーすることはもちろん、実施に向けて人の派遣やノウハウの提供など、あらゆる手段を尽くし、未実施という選択肢がないように取組むべきと考えます。 3. 選挙初日のいわゆる第一声については、手話通訳をお願いする予定であり、また、政見放送においても、手話通訳及び字幕によって、耳の聞こえにくい方への配慮をする予定です。 個人演説会は、会そのものを実施する、実施しないも含めて各候補者の判断になりますが、 その他の街頭演説なども含めて、可能な限り、情報保障や配慮がなされるよう、取り組んでいく考えです。 4. 聴覚に障害のある方にとって、電話等の音声による呼びかけの代替手段として、FAXやメール等の文字による呼びかけを認めることは、重要なことであると考えます。 公職選挙法も、この間、一部が改正されていますが、障害者への配慮をはじめ、合理的配慮が十分に担保されているとは言えません。 選挙権、被選挙権の行使、選挙運動は民主主義社会にとって、大変重要な権利のひとつです。こうした観点から、東京都独自に何ができるのかも含め、検討していくべきだと考えています。5. 「法の下の平等」が守られていないと考えています。 テレビの政見放送における手話は、規則改正などの対応が求められます。 また、街頭演説などに際しても、手話通訳や要約筆記の数が少ないことに加え、その費用も候補者の自己負担であることなどから、候補者の主張を聴覚障害者に周知することが難しい状況になっています。 こうした認識のもと、選挙における「法の下の平等」が守られるよう国政とも連携しながら 制度改正等に取り組んでいきたいと考えています。6. 今年11月15日から、いよいよ「デフリンピック東京2025デフリンピック大会」が開催されます。 私たちは、これをひとつの契機として、情報保障の取り組みを大きくレベルアップさせるとともに、聴覚障害に対する都民・国民の理解をより一層進め、互いに尊重し合う社会の実現に向けて取り組んでいきたいと考えています。 |
●日本共産党東京都委員会 1. 今年3月の都議会本会議で、東京都障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する条例が全会一致で可決・成立しました。同条例は、日本共産党都議団を含む超党派のプロジェクトチームで検討を重ねてきたものです。 障害があってもなくても、また、どのような障害であっても、必要な情報を同じように受け取ることができて、コミュニケーションを図れるということは誰にも保障されるべき権利です。この権利が同条例の前文に位置づけられたことは、たいへん重要です。 また同条例は、障害者や都民の方々の意見を踏まえて、実施状況を確認していくこと、そして、3年後の見直しも障害者の方の意見を聞くことを位置づけたことも、たいへん重要です。同条例は作って終わりではなく、同条例を使って具体的にどう改善していくのかが重要です。皆さんと都民の意見をよく聞いて、ご一緒に取り組みを進めていく決意です。 2. 情報保障の地域間格差をなくすことは重要だと考えます。 東京都が広域性・公益性を理由に派遣の範囲を狭く限定している現状は改めさせる必要があります。障害者が障害者でない人と同じように意思疎通をできるようにするという考え方を基本に、幅広く利用できる制度とするべきです。 また、個人に対する緊急性や専門性が求められる場合の派遣や、事業を実施していない区市町村を補完する派遣も行うべきです。 3. 障害者が障害者でない人と同じように選挙に関する情報にアクセスできるようにすることは、参政権を保障する上で重要です。 演説会で手話通訳や盲ろう者向け通訳・介助、音声ループの活用、作成する動画に字幕をつける、などの取り組みを可能なかぎり進めます。 4. FAXやメールでの投票依頼が制限されていることは、聴覚障害者にとってとりわけバリアとなっており、参政権が侵害されています。そもそも選挙運動は自由であるべきであり、公職選挙法の「文書活動の規制」を撤廃し、FAXやメールの利用などを自由にするべきだと考えています。 5. 障害者権利条約、障害者差別解消法により定められた障害のある人の投票における環境整備と合理的配慮を行い、障害者の参政権を保障すべきです。日本共産党は、ご指摘にある、選挙の候補者や議員活動での介助、代読、手話通訳などの合理的配慮を保障することを、政府に対して強く求めています。 6. 軽度・中等度の難聴者への補聴器購入費に対する公費助成の実現に取り組みます。日本では公費助成の対象者が重度の難聴者に限られているため、難聴者の補聴器利用率は欧米諸国と比べて非常に低くなっています。日本共産党は、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション法が2022年5月の衆院本会議で全会一致で可決・成立したことを踏まえ、同法成立を機に加齢性難聴の対策も進め、補聴器修理費用も含めた国の支援を求めています。より幅広く助成を行うことで、難聴者の聞こえへの支援を強化します。 東京都内では独自に補聴器購入費助成を行う自治体が増えていますが、未実施の自治体も残されています。また、実施しているところも年齢制限、所得制限が残っていたり、金額が少なかったりという課題を抱えているところが少なくありません。都による区市町村への補助を拡充し、住む場所にかかわらず、補聴器による聞こえの支援を受ける権利が保障されるようにします。 |
●東京・生活者ネットワーク(都議会生活者ネットワーク) 1. この条例は、2022年の手話言語条例を踏まえてできたものです。どちらも議員提案の条例であり、生活者ネットワークも提案者になりました。今後は、条例を活用してコミュニケーションツールが十分に使えるようにしていく必要があります。 2. 手話通訳等の派遣は、地域では当該自治体が、広域の場合は東京都が実施することになっていますが、実際には、聴覚障害者団体以外の市民団体が開催するイベントへの派遣が実施されなかったり、都が派遣するためのハードルは高いと聞いています。条例の施行もあり、今後は活用しやすくしていく必要があると考えます。 3. 一部の街頭演説で手話通訳を実施する予定です。対応できる場面を増やしていくことは課題と思っています。 4. ご指摘のとおりだと思います。 5. 上記4もそうですが、公職選挙法の規定はおかしいところや時代に合わないところがどんどん出てきています。音声変換など新たなアプリ・機器も活用して、政治参加を広げることが重要であると考えます。 6. 災害時の情報伝達に課題があるため、移動中など状況に応じた対策に取り組みます。 |
●都民ファーストの会 1. 都民ファーストの会も提案者となったこの条例の制定は、誰一人取り残さない情報保障を具現化する重要な一歩です。特に、聴覚障害者をはじめとする情報・コミュニケーションに困難を抱える方々の権利保障において、東京都で先進的な取り組みを示したことは意義深いものであると認識しています。条例の7月1日の施行に向けて、基礎自治体との連携強化による施策の均質化、手話言語の普及促進、デジタルを活用した情報アクセス環境の整備など実効性のある施策を展開し、条例の趣旨が真に実現されるように取り組んでまいります。 2. 東京都の意思疎通支援事業の充実を積極的に推進すべきと考えます。ご指摘の地域格差や広域派遣事業の課題は、聴覚障害者の社会参加を阻害しかねない問題です。都事業として、区市町村で対応困難な専門性・緊急性の高い場面への派遣体制整備、事業未実施自治体への後押し、異なる地域からの参加者がいる活動への派遣拡大など、都内全域での均質なサービス提供を目指します。通訳者の育成・処遇改善による人材確保も重要課題として取り組み、予算措置も含めて都民の情報アクセス権を保障する東京を実現してまいります。 3. 聴覚障害者・盲ろう者の皆様にも等しく政治参加の機会を保障することは、候補者としての責務であると考えます。また党主催の勉強会などでも手話通訳や要約筆記を行ってきました。現行の公職選挙法の課題はありますが、動画配信の際の字幕の挿入、ウェブサイトのアクセシビリティ向上など可能な範囲で最大限の配慮を行い、すべての有権者が政策を理解し、投票行動を行える環境づくりに努めてまいります。 4. 公職選挙法を改正する必要があると考えます。都議会から国政への働きかけを通じて、公職選挙法の改正を求めてまいります。また、東京都として可能な範囲での環境整備や、他の自治体との連携による制度改善の要請も行ってまいります。すべての都民が平等に政治参加できる社会の実現に向けて積極的に取り組んでまいります。 5. 公職選挙法を改正する必要があると考えます。都議会から国政への働きかけを通じて、公職選挙法の改正を求めてまいります。政見放送時の通訳や字幕の付与による情報保障の義務化、通訳者を公的な情報保障支援者と位置付けること、中立性を確保した制度設計などが必要であると考えます。すべての都民が平等に政治参加できる社会の実現に向けて積極的に取り組んでまいります。 6. 都民ファーストの会は2025年東京デフリンピック開催を契機として、聴覚障害者福祉施設を一層向上させてまいります。大会レガシーとして手話言語の普及拡大、聴覚障害者スポーツ環境の継続的整備、国際交流拠点としての東京確立を目指します。重点施策としては、障害者福祉施策の所得制限撤廃、都庁での手話通訳体制拡充、デジタル技術活用の遠隔通訳システムの展開、緊急時情報伝達の多様化を推進します。また、手話言語を活用した教育環境整備、企業啓発による職業選択拡大、文化・芸術活動参加機会の創出にも取り組みます。デフリンピック開催都市として、聴覚障害者が真に活き活きと暮らせる東京の実現に全力で取り組んでまいります。 |
●東京都議会自由民主党 1. 障害者による情報の取得及び利用ならびに意思疎通に係る施策を総合的に推進することにより、東京で暮らし、東京を訪れる全ての人が、障害の有無によって分け隔てなく互いに意思を伝え、理解し、尊重しあいながら安心して生活することができる共生社会を実現する必要があります。 2. 東京都の手話通訳者等の派遣事業都等、聴覚障害者の支援を補完するため、意思疎通支援者養成講習会の充実を図る必要があると考えます。 3. 各種選挙において、各候補者の政策をアピールする場として、個人演説会や街頭演説会等がありますが、今回の都議選においても、障害者に配慮した選挙活動を行うことが重要と考えます。 4. 公職選挙法等の制約はありますが、候補者誰もが、選挙活動がしやすく、政策を訴えることができる状況になることが、必要であると考えます。 5. 質問事項4と同様 6. 東京都手話言語条例及び東京都障害者情報コミュニケーション条例の理念・目的を遵守し、共生社会実現に向けた取組みを推進してまいります。 |