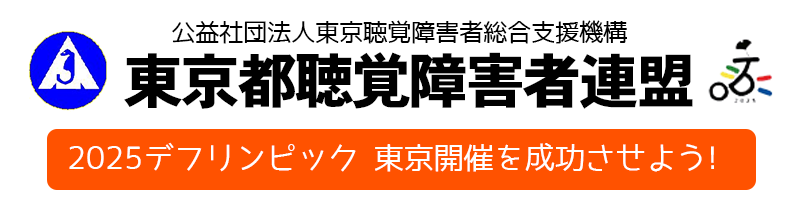7月21日投票予定の参議院議員選挙を前に、聴覚障害者制度改革推進東京本部として、各政党・立候補予定者に対して、聴覚障害者の福祉施策や情報・コミュニケーション支援についてお尋ねするアンケートを実施しました。
以下に各政党・各立候補予定者にお送りした依頼文、アンケート本文、各党からの回答を掲載します。
掲載順は到着順です。回答がなかったところは(未回答)としています。
各党の考え方を理解し、皆様が投票する際の参考としていただければ幸いです。
2013年7月3日
2013年6月30日 党 様 聴覚障害者制度改革対策東京本部 (東京都聴覚障害者福祉対策会議) 代 表 宮 本 一 郎 (公印省略) 障害者福祉施策に関する公開質問
日頃、聴覚障害者福祉向上にご尽力賜り、厚くお礼申し上げます。 私たち「聴覚障害者制度改革推進東京本部」は、聴覚障害当事者団体とその支援団体の8団体によって構成し、聴覚障害者福祉に係わる施策をより良いものにするべく活動しております。特に、障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話普及等を実現するための法整備を求めているところです。 2011年7月に「改正障害者基本法」が成立し、そこには「言語(手話を含む)」と規定されるなど、聴覚障害者の社会参加を進める上での大きな一歩を踏み出しておりますが、「障害者自立支援法」は多くの課題を引き継いだまま本年4月より「障害者総合支援法」として施行されました。 また、先日成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)は、我が国の障害者権利条約批准を進めるにあたって、大きく前進することが期待されています。 2012年12月の衆議院選挙を経て、今回の参議院選挙においても各政党の聴覚障害者福祉施策についての関心はますます高まってきております。 つきましては、皆様の見解を広く関係者に周知いたしたく、お忙しいところを大変恐縮ですが別紙の質問用紙に根拠となる理由を付してご記入の上、7月3日(水)までにメールまたはFAXにてご回答を頂きたくお願いいたします。 尚、ご回答の結果はご回答の有無、内容を政党別に整理し、また頂いたご回答内容は原文のまま当中央本部ウェブサイトの他、各構成団体の機関紙などに掲載させて頂くとともに、報道機関等へ発表していく予定です。 聴覚障害者制度改革東京本部 (東京都聴覚障害者福祉対策会議) 構成団体:社団法人東京都聴覚障害者連盟、NPO法人東京都中途失聴・難聴者協会、NPO法人東京盲ろう者友の会、東京都手話通訳問題研究会、東京都登録要約筆記者の会、全国要約筆記問題研究会東京支部、東京都手話サークル連絡協議会、東京都要約筆記サークル連絡会 事務局:〒150-0011 渋谷区東1~23~3 東京聴覚障害者自立支援センター3階 (社)東京都聴覚障害者連盟内 電話 03-5464-6055 FAX 03-5464-6057 E-mail tokyo@deaf.to ・質問事項のお問い合わせは、推進東京本部事務局までお願いします。 ・7月3日(水)までに推進東京本部事務局までFAXかEメールにてご回答くださるようお願いいたします。 1.障害者総合支援法について 障害者福祉は利用者負担なしで、全国共通の仕組みを作るべきだと思います。この度、成立した障害者総合支援法には「視聴覚障害者の意思疎通支援事業」が含まれましたが、地域間格差や不十分な予算措置等の問題は依然として残ったままです。障害者総合支援法は施行後3年以内に検討事項と附帯決議の具体化を決めています。 今後の障害者総合支援法の見直しや拡充に対するご見解をお聞かせください。 2.障害者総合支援法における都道府県・市町村等の意思疎通支援事業について 今回、厚生労働省の補助事業として、厚生労働省と全日本ろうあ連盟をはじめとする関係者等で協議を重ね、意思疎通支援者の派遣に係るモデル要綱およびガイドラインを作成しました。 3.行政サービスのアクセシブルな利用について 身体障害者手帳を持たない聴覚障害者、聴覚に障害のある者と意思疎通の必要のある者など、誰もが自由に利用できる制度には至っておりません。また、聴覚障害者が自分の希望するコミュニケーション手段を使ってのサービス提供を受けるに至っていない現状があります。 4.インターネット選挙運動(以下、「ネット選挙」とする)について 4-1)今春の法改正でネット選挙が認められるようになって、初めての国政選挙となります。 4-2)障害者総合支援法の意思疎通支援事業において、自治体の裁量で、選挙や政治活動への手話通訳および要約筆記の派遣が可能となりましたが、自治体の派遣要綱では派遣を不可とするところが多い現状にあります。上記について、貴党はどのようなご見解をお持ちですか。 5.政見放送への手話通訳・字幕付与の義務化、選挙時の情報保障について 5-1)別紙①の通り、政見放送への手話通訳・字幕付与について、衆議院・参議院共に統一されておりません。 5-2)また、このたびの選挙において、政見放送、個人演説会、選挙公報など貴党の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか? 6.障害者差別解消法について 本年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が国会に提出されました。障害者差別解消法における、情報アクセスやコミュニケーションの保障への「合理的配慮」、紛争解決にあたる機関の在り方等について、貴党のご見解をお聞かせください。 7.障害者差別解消法について 本年4月、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」(障害者雇用促進法改正法案)が閣議決定、国会に上程されましたが、日本における企業の法定雇用率に対する取組みや、ハローワークにおける手話協力員制度および雇用・労働分野における聴覚障害者専門の相談支援のための職場適応援助者(ジョブコーチ)事業を拡充させるために、貴党のご見解をお聞かせください。 8.情報・コミュニケーションを保障する法律・制度の必要性について 障害者福祉以外に医療、福祉全般、教育(高等教育含む)、司法、就労、放送・通信など社会のあらゆる分野で障害者の情報アクセスやコミュニケーションを権利として保障する法制度は、すべての障害者の生命や社会参加を保障するという重要性にも関わらず、確立していません。情報アクセシビリティを確立させる為の環境整備(機器・システム・サービスの標準化・規格化、放送・映像への手話通訳および字幕の付与等)を諮るとともに、情報アクセスやコミュニケーションを保障する法制定に向けて、貴党はどのようにお考えか見解をお聞かせください。。 9.その他 聴覚障害者福祉施策について、貴党が特に取組みたいとされていることをお聞かせください。 ご協力ありがとうございました。
|
【公開質問状に対する回答】
※いずれも原文のまま掲載しています。
※以下、回答到着順です。敬称は省略させていただきます。
●民主党 鈴木 寛
●自民党 丸川珠代
●無所属 山本 太郎
●無所属 大河原まさこ
●日本共産党 吉良よし子
※「貴党」のご見解をうかがうとありますが、すべて民主党所属参議院議員鈴木寛の議員の立場からの回答を致します。この点あらかじめご了解ください。
<質問事項>
1.障害者総合支援法について
障害者福祉は利用者負担なしで、全国共通の仕組みを作るべきだと思います。この度、成立した障害者総合支援法には「視聴覚障害者の意思疎通支援事業」が含まれましたが、地域間格差や不十分な予算措置等の問題は依然として残ったままです。障害者総合支援法は施行後3年以内に検討事項と附帯決議の具体化を決めています。
今後の障害者総合支援法の見直しや拡充に対するご見解をお聞かせください。
回答)
障害者総合支援法は、本来民主党が目指した障害者自立支援法廃止と、障害者総合福祉法の制定の観点からはまだほど遠く、自民党・公明党が障害者自立支援法の廃止を主張する限り法案には賛成しないと強硬な主張をしたために生じた妥協の産物であると認識しています。私は、民主党が掲げた障害者総合福祉法(民主党政権下の障害者制度改革推進会議で定めた骨格提言の内容にほぼ近いもの)の実現に向けて努力します。
2.障害者総合支援法における都道府県・市町村等の意思疎通支援事業について
今回、厚生労働省の補助事業として、厚生労働省と全日本ろうあ連盟をはじめとする関係者等で協議を重ね、意思疎通支援者の派遣に係るモデル要綱およびガイドラインを作成しました。
しかし、「手話通訳設置事業」については、すでに多くの都道府県が行っているにもかかわらず、都道府県の必須事業とはなりませんでした。
また、設置される手話通訳者の身分、労働条件等が市町村によって異なっている状況です。
その現状と照らし合わせ、施行後3年以内の見直し検討に向けて、手話通訳者および要約筆記者の養成・認定事業や設置事業、そして盲ろう者通訳・介助者の養成、派遣事業のモデル要綱およびガイドラインを作成していく必要があります。これについて、貴党のご見解をお聞かせください。
回答)
少なくとも政治の立場においては、聴覚障害の方への政治参加の手段として手話通訳は重要であると認識しておりますが、現状の公職選挙法上、手話通訳は公費負担の対象とはなっておらず、候補者の裁量に委ねられている状況にあります。少なくとも選挙や納税の場面などの国民の重要な政治参加の場面や公の義務の行使の場面では、できるだけ手話通訳や要約筆記を拡充する必要があると考えます。
3.行政サービスのアクセシブルな利用について
身体障害者手帳を持たない聴覚障害者、聴覚に障害のある者と意思疎通の必要のある者など、誰もが自由に利用できる制度には至っておりません。また、聴覚障害者が自分の希望するコミュニケーション手段を使ってのサービス提供を受けるに至っていない現状があります。
国民である以上、障害の有無にかかわらず行政のサービスを受けられるべきであり、それを提供する義務が行政機関にはあると考えます。
例えば、情報アクセスのバリア解消のため、都道府県市町村の福祉事務所等に手話で相談できるケースワーカー等の相談員の配置や地方自治体の窓口における筆談対応の職員研修、手話のできる職員の配置等を推進する必要があります。
行政機関のアクセシブルな利用促進について、貴党はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
行政サービスは、実際の窓口は各自治体であるため、自治体ごとの取り組みのばらつきが問題になっていると認識しています。一方で地域主権の観点からは各自治体ができるだけ自主的に運営することが求められており、国としては情報アクセスのバリア解消の必要性を理解してもらうよう努めるべきと考えます。
4.インターネット選挙運動(以下、「ネット選挙」とする)について
4-1)今春の法改正でネット選挙が認められるようになって、初めての国政選挙となります。
これまで、FAXやメールでの選挙運動等は認められなかったことを鑑みると、選挙に関するアクセシビリティとしては大変有効であると考えます。しかし、電話の出来ない聴覚障害者の候補者がFAXやメールで投票依頼をすることは現在も認められておりません。上記について、貴党はどのようなご見解をお持ちですか。
4-2)障害者総合支援法の意思疎通支援事業において、自治体の裁量で、選挙や政治活動への手話通訳および要約筆記の派遣が可能となりましたが、自治体の派遣要綱では派遣を不可とするところが多い現状にあります。上記について、貴党はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
4-1)について
インターネットとメールやFAXの垣根は極めてあいまいであり、民主党としてはメールでの選挙運動の解禁も求めています。一方でファクシミリは相手の通信資源を使う側面もあるため、迷惑行為になる恐れもあり得ますので、慎重な検討が必要であると考えています。
4-2)について
障害者権利条約に基づく政治参加の自由の拡充の観点からは、派遣を増やすべきと考えます。
5.政見放送への手話通訳・字幕付与の義務化、選挙時の情報保障について
5-1)別紙①の通り、政見放送への手話通訳・字幕付与について、衆議院・参議院共に統一されておりません。
同じ国民でありながら候補者を選ぶ権利、参政権を行使するための情報の入手が制限されている状況を、貴党はどのようにお考えか、見解をお聞かせ下さい。
5-2)また、このたびの選挙において、政見放送、個人演説会、選挙公報など貴党の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?
回答)
5-1)について
政見放送の手話通訳・字幕付与は政治参加の観点から必須とすべきと考えます。
5-2)について
できるだけ聴覚障害者・盲ろう者に対する情報提供を務めています。具体的には、大田区で実施した決起大会では手話通訳を取り入れていますが、費用面の問題もあり、まだ完全実施とはなっていません。公費負担による完全実施が求められます。
6.障害者差別解消法について
本年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が国会に提出されました。障害者差別解消法における、情報アクセスやコミュニケーションの保障への「合理的配慮」、紛争解決にあたる機関の在り方等について、貴党のご見解をお聞かせください。
回答)
障害者権利条約に基づく差別の禁止、および憲法14条の平等の観点からは、国内法の制定が待たれる状況であり、その意味では本法律はその一里塚であると認識しております。
7.障害者差別解消法について
本年4月、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」(障害者雇用促進法改正法案)が閣議決定、国会に上程されましたが、日本における企業の法定雇用率に対する取組みや、ハローワークにおける手話協力員制度および雇用・労働分野における聴覚障害者専門の相談支援のための職場適応援助者(ジョブコーチ)事業を拡充させるために、貴党のご見解をお聞かせください。
回答)
障害者の法定雇用率が本年4月から2%に上昇し、かつ適用事業所が50人以上と拡大したところですが、企業の法定雇用率向上のための課題は、身体障害者の雇用の機会が広がる一方で、聴覚・視覚障害者や知的障害者の雇用率が伸びないという歪みが生じていると認識しています。これら事業の拡充のためには、未達成企業の公表などの罰則的なアプローチだけでは不十分であり、介助者や側面支援制度の拡充が必要であると考えています。職場適応援助者事業はその一端であり、拡充することには賛成していますが、援助者の担い手の確保や財政などの課題が存在していると認識しています。
8.情報・コミュニケーションを保障する法律・制度の必要性について
障害者福祉以外に医療、福祉全般、教育(高等教育含む)、司法、就労、放送・通信など社会のあらゆる分野で障害者の情報アクセスやコミュニケーションを権利として保障する法制度は、すべての障害者の生命や社会参加を保障するという重要性にも関わらず、確立していません。情報アクセシビリティを確立させる為の環境整備(機器・システム・サービスの標準化・規格化、放送・映像への手話通訳および字幕の付与等)を諮るとともに、情報アクセスやコミュニケーションを保障する法制定に向けて、貴党はどのようにお考えか見解をお聞かせください。。
回答)
今回のインターネット選挙は、私の主張からは不十分でありつつも、民主党の法案責任者として法律の制定に漕ぎ着けた自負があり、今後も障害者の方々へも含めて情報・コミュニケーションの拡充のために努力してまいります。
●自民党 丸川珠代
※参議院選を控えあまりに時間がなく、また党の見解ということもあり遅くになりましたが、残念ながら回答途中で失礼いたします。
<質問事項>
1.障害者総合支援法について
障害者福祉は利用者負担なしで、全国共通の仕組みを作るべきだと思います。この度、成立した障害者総合支援法には「視聴覚障害者の意思疎通支援事業」が含まれましたが、地域間格差や不十分な予算措置等の問題は依然として残ったままです。障害者総合支援法は施行後3年以内に検討事項と附帯決議の具体化を決めています。
今後の障害者総合支援法の見直しや拡充に対するご見解をお聞かせください。
回答)
党の見解ということですので、党政調の見解として下記に記します。
自由民主党では総合政策集にて、次の通り障害者政策について記載し、党としての障害者施策の方向性を明確にしております。
これまで同様に、今後とも関係の皆様のご意見を伺いながら、共に検討を進めて参りたいと考えておりますので、引き続きご指導ご鞭撻ならびに自民党へのご支援を賜りますようお願い申し上げます。
【参考】総合政策集(抄)
263 障害者の方への施策の推進
自民党は、障害程度区分から障害支援区分に修正するなど『障害者自立支援法』の改正に精力的に取り組み、『障害者総合支援法』を成立させました。その着実な推進を図りつつ、国と地方の適切な役割分担の下、地域の実情を踏まえながら、計画的なサービスの基盤整備を図ります。
また、自民党が主導した『障害者優先調達推進法(ハート購入法)』を着実に実施する等雇用の促進に努めます。
さらに、精神障害のある人が地域で安心して暮らすことができるよう、『精神保健福祉法』の改正をはじめとした精神保健医療福祉施策の改革に取り組むとともに、障害福祉サービスの利用の観点から、成年後見制度の活用をさらに進めます。
自民党は、障害の有無にかかわらず、国民の誰もが相互に人格と個性を尊重し支えあう社会を実現するため、『障害者基本法』の改正に主導的に取り組みましたが、さらにその具体化を図る観点から、『障害を理由とした差別の解消の推進に関する法律案(障害者差別解消法)』の制定と『障害者雇用促進法』の改正に取り組み、法案を成立させました。今後、幅広い国民の共感と理解を得ながら、これらの法案の成立、施行の推進を図ります。
引き続き、障害のある人の自立と社会参加のための施策を積極的に推進してまいります。
2.障害者総合支援法における都道府県・市町村等の意思疎通支援事業について
今回、厚生労働省の補助事業として、厚生労働省と全日本ろうあ連盟をはじめとする関係者等で協議を重ね、意思疎通支援者の派遣に係るモデル要綱およびガイドラインを作成しました。
しかし、「手話通訳設置事業」については、すでに多くの都道府県が行っているにもかかわらず、都道府県の必須事業とはなりませんでした。
また、設置される手話通訳者の身分、労働条件等が市町村によって異なっている状況です。
その現状と照らし合わせ、施行後3年以内の見直し検討に向けて、手話通訳者および要約筆記者の養成・認定事業や設置事業、そして盲ろう者通訳・介助者の養成、派遣事業のモデル要綱およびガイドラインを作成していく必要があります。これについて、貴党のご見解をお聞かせください。
回答)
都道府県に関わることでそれを踏まえて党としての見解を記します。
障害者総合支援法には、障害者等の支援に関する施策を段階的に講じていくため、施行後3年を目途として検討すべき事項が定められており、その検討項目の一つに「手話通訳などを行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害の為、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方」が含まれています。ご指摘の内容については、障害者ご本人やご家族など関係者のご意見をいただきながら、この検討の中で議論を進めていくことが重要と考えており、自民党としても厚労省に働きかけていきます。
3.行政サービスのアクセシブルな利用について
身体障害者手帳を持たない聴覚障害者、聴覚に障害のある者と意思疎通の必要のある者など、誰もが自由に利用できる制度には至っておりません。また、聴覚障害者が自分の希望するコミュニケーション手段を使ってのサービス提供を受けるに至っていない現状があります。
国民である以上、障害の有無にかかわらず行政のサービスを受けられるべきであり、それを提供する義務が行政機関にはあると考えます。
例えば、情報アクセスのバリア解消のため、都道府県市町村の福祉事務所等に手話で相談できるケースワーカー等の相談員の配置や地方自治体の窓口における筆談対応の職員研修、手話のできる職員の配置等を推進する必要があります。
行政機関のアクセシブルな利用促進について、貴党はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
同上
与党ワーキングチームで検討を進めてまいりました障害者差別解消法が本年6/19に成立しました。その中で、差別的な取り扱いの禁止や合理的配慮の不提供の禁止を国や行政機関については義務として規定しています。
平成28年4月の施行に向けて、有識者らで組織する障害者政策委員会のご意見を聞きながら政府として基本方針を策定し、各省庁でガイドラインを策定していきます。
●無所属 山本 太郎
<質問事項>
1.障害者総合支援法について
障害者福祉は利用者負担なしで、全国共通の仕組みを作るべきだと思います。この度、成立した障害者総合支援法には「視聴覚障害者の意思疎通支援事業」が含まれましたが、地域間格差や不十分な予算措置等の問題は依然として残ったままです。障害者総合支援法は施行後3年以内に検討事項と附帯決議の具体化を決めています。
今後の障害者総合支援法の見直しや拡充に対するご見解をお聞かせください。
回答)
難病支援など新たに加えられた点などは評価できるが、次のような課題があります。
① 益負担が継続されたこと。利用者負担が見直されていない。
② 三障害(知的、身体、精神)の統一的施策が不十分
③ 障害者が「権利の主体」となる法律となっていない。
また、聴覚障害者の情報保障や手話通訳設置(派遣)、要約派遣筆記者等の対応に関しては最低限拡充していく必要があります。今後の支援法見直しについては情報保障等の地域格差解消や聴覚障害当事者や手話通訳者、要約筆記者等の現場の声や実態把握をより進めていく工夫や努力が必要であり、課題や問題の共有が最優先になります。聴覚障害者に関しては特に検討や協議の場を早急に立ち上げることが、最低限支援法見直しに関しての要件にする必要があります。
2.障害者総合支援法における都道府県・市町村等の意思疎通支援事業について
今回、厚生労働省の補助事業として、厚生労働省と全日本ろうあ連盟をはじめとする関係者等で協議を重ね、意思疎通支援者の派遣に係るモデル要綱およびガイドラインを作成しました。
しかし、「手話通訳設置事業」については、すでに多くの都道府県が行っているにもかかわらず、都道府県の必須事業とはなりませんでした。
また、設置される手話通訳者の身分、労働条件等が市町村によって異なっている状況です。
その現状と照らし合わせ、施行後3年以内の見直し検討に向けて、手話通訳者および要約筆記者の養成・認定事業や設置事業、そして盲ろう者通訳・介助者の養成、派遣事業のモデル要綱およびガイドラインを作成していく必要があります。これについて、貴党のご見解をお聞かせください。
回答)
まず基本がナショナルミニマムとしての、全国的な最低基準は必要。その上で市町村の自治によって上乗せを決めていくことが重要です。
この問題に関しては地域格差が大きな課題になっています。特に情報保障に関する人材育成や環境整備が急務です。また、全体的に情報保障に関しては最低限の整備も整っていないことの理解が不足しています。
3.行政サービスのアクセシブルな利用について
身体障害者手帳を持たない聴覚障害者、聴覚に障害のある者と意思疎通の必要のある者など、誰もが自由に利用できる制度には至っておりません。また、聴覚障害者が自分の希望するコミュニケーション手段を使ってのサービス提供を受けるに至っていない現状があります。
国民である以上、障害の有無にかかわらず行政のサービスを受けられるべきであり、それを提供する義務が行政機関にはあると考えます。
例えば、情報アクセスのバリア解消のため、都道府県市町村の福祉事務所等に手話で相談できるケースワーカー等の相談員の配置や地方自治体の窓口における筆談対応の職員研修、手話のできる職員の配置等を推進する必要があります。
行政機関のアクセシブルな利用促進について、貴党はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
行政サービス、行政情報のバリア解消は、障害者の権利として保障が必須。
この利用促進に関しては人材育成が重要です。福祉系の大学や専門学校等の教育専門機関での人材育成を整備、推進していくとともに、公共機関での情報アクセスのバリア解消のための職員教育が重要です。また、現手話通訳者や要約筆記者等の現場の声を聞くこと、課題や問題の把握が最優先です。同時に行政機関こそが最優先した環境整備が急務です。
4.インターネット選挙運動(以下、「ネット選挙」とする)について
4-1)今春の法改正でネット選挙が認められるようになって、初めての国政選挙となります。
これまで、FAXやメールでの選挙運動等は認められなかったことを鑑みると、選挙に関するアクセシビリティとしては大変有効であると考えます。しかし、電話の出来ない聴覚障害者の候補者がFAXやメールで投票依頼をすることは現在も認められておりません。上記について、貴党はどのようなご見解をお持ちですか。
4-2)障害者総合支援法の意思疎通支援事業において、自治体の裁量で、選挙や政治活動への手話通訳および要約筆記の派遣が可能となりましたが、自治体の派遣要綱では派遣を不可とするところが多い現状にあります。上記について、貴党はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
4-1 法改正されたインターネット選挙運動こそ、聴覚障害者のために情報保障が改善されるものにならなければならなかった課題です。その重要性を今後も理解してもらう努力が必要であり、ていねいな議論が大切です。
4-2 まずは最低限、必要性を理解していない自治体が多いことが大きな問題です。その意味では聴覚障害者の声を聞き、情報格差を改善していくことが必須です。
5.政見放送への手話通訳・字幕付与の義務化、選挙時の情報保障について
5-1)別紙①の通り、政見放送への手話通訳・字幕付与について、衆議院・参議院共に統一されておりません。
同じ国民でありながら候補者を選ぶ権利、参政権を行使するための情報の入手が制限されている状況を、貴党はどのようにお考えか、見解をお聞かせ下さい。
5-2)また、このたびの選挙において、政見放送、個人演説会、選挙公報など貴党の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?
回答)
5-1 政見放送への手話通訳・字幕付与は必須です。
5-2 今回もボランティア選挙を行っているため、できるだけの情報提供になります。必要に応じての個別での対応は支持者等の協力により、実施します。
6.障害者差別解消法について
本年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が国会に提出されました。障害者差別解消法における、情報アクセスやコミュニケーションの保障への「合理的配慮」、紛争解決にあたる機関の在り方等について、貴党のご見解をお聞かせください。
回答)
解消法が情報アクセスやコミュニケーション保障からも情報保障の改善のキッカケになるように、協議や検討の場の立ち上げや必須です。また情報アクセスやコミュニケーション保障等への「合理的配慮」等については内容を注視し、努力義務にとどめることなく、同法の推進や実行をチェックする等の機関が必要です。
7.障害者差別解消法について
本年4月、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」(障害者雇用促進法改正法案)が閣議決定、国会に上程されましたが、日本における企業の法定雇用率に対する取組みや、ハローワークにおける手話協力員制度および雇用・労働分野における聴覚障害者専門の相談支援のための職場適応援助者(ジョブコーチ)事業を拡充させるために、貴党のご見解をお聞かせください。
回答)
まずは改正法推進の観点から聴覚障害者の就労実態を把握する必要があります。その上で職場適応援助者(ジョブコーチ)事業の拡充や雇用・労働分野における聴覚障害者専門の相談支援の充実が基本です。
8.情報・コミュニケーションを保障する法律・制度の必要性について
障害者福祉以外に医療、福祉全般、教育(高等教育含む)、司法、就労、放送・通信など社会のあらゆる分野で障害者の情報アクセスやコミュニケーションを権利として保障する法制度は、すべての障害者の生命や社会参加を保障するという重要性にも関わらず、確立していません。情報アクセシビリティを確立させる為の環境整備(機器・システム・サービスの標準化・規格化、放送・映像への手話通訳および字幕の付与等)を諮るとともに、情報アクセスやコミュニケーションを保障する法制定に向けて、貴党はどのようにお考えか見解をお聞かせください。。
回答)
情報・コミュニケーション保障に関する問題や課題は聴覚障害者だけではなく、福祉・医療・教育等のあらゆる分野において、重要となります。社会全体の課題としての認識を強めていく必要があります。
9.その他
聴覚障害者福祉施策について、貴党が特に取組みたいとされていることをお聞かせください。
回答)
情報保障と手話通訳者、要約筆記者等の人材育成、聴覚障害者への理解等が不足しています。最低限の保障ができていないことへの問題を呼びかけていきます。聴覚障害者や手話通訳者、要約筆記者等がさまざまな場面で当事者参加・参画ができるようにお互いに声を形にしていきましょう。
●無所属 大河原まさこ
<質問事項>
1.障害者総合支援法について
障害者福祉は利用者負担なしで、全国共通の仕組みを作るべきだと思います。この度、成立した障害者総合支援法には「視聴覚障害者の意思疎通支援事業」が含まれましたが、地域間格差や不十分な予算措置等の問題は依然として残ったままです。障害者総合支援法は施行後3年以内に検討事項と附帯決議の具体化を決めています。
今後の障害者総合支援法の見直しや拡充に対するご見解をお聞かせください。
回答)
障害者総合支援法における「意思疎通支援を行う者を養成する事業」をはじめとした事業の実施にあたっては、自治体・地域間での相違(格差)が懸念されていますが、よりよい自治体・地域へと全国的に向上していくようなしくみが必要だと考えます。法の見直しにあたっては、障害者差別解消法も制定されたことから、その施行に向けて具体的な検討がなされますので、その動向などともあいまって、よりよい制度となるよう見直しが必要な部分については速やかに見直すべきだと考えます。
2.障害者総合支援法における都道府県・市町村等の意思疎通支援事業について
今回、厚生労働省の補助事業として、厚生労働省と全日本ろうあ連盟をはじめとする関係者等で協議を重ね、意思疎通支援者の派遣に係るモデル要綱およびガイドラインを作成しました。
しかし、「手話通訳設置事業」については、すでに多くの都道府県が行っているにもかかわらず、都道府県の必須事業とはなりませんでした。
また、設置される手話通訳者の身分、労働条件等が市町村によって異なっている状況です。
その現状と照らし合わせ、施行後3年以内の見直し検討に向けて、手話通訳者および要約筆記者の養成・認定事業や設置事業、そして盲ろう者通訳・介助者の養成、派遣事業のモデル要綱およびガイドラインを作成していく必要があります。これについて、貴党のご見解をお聞かせください。
回答)
「手話通訳設置事業」をはじめとする、コミュニケーションにおけるさまざまなハンディをお持ちの方々に対する支援事業等については、基本的に必須の事業とすべきであり、そのうえで「合理的配慮等」の考え方に則り、多様な事業を検討実施すべきであると考えます、その促進のためにも、一定の基準となるガイドライン等の作成は必要だと考えます。
3.行政サービスのアクセシブルな利用について
身体障害者手帳を持たない聴覚障害者、聴覚に障害のある者と意思疎通の必要のある者など、誰もが自由に利用できる制度には至っておりません。また、聴覚障害者が自分の希望するコミュニケーション手段を使ってのサービス提供を受けるに至っていない現状があります。
国民である以上、障害の有無にかかわらず行政のサービスを受けられるべきであり、それを提供する義務が行政機関にはあると考えます。
例えば、情報アクセスのバリア解消のため、都道府県市町村の福祉事務所等に手話で相談できるケースワーカー等の相談員の配置や地方自治体の窓口における筆談対応の職員研修、手話のできる職員の配置等を推進する必要があります。
行政機関のアクセシブルな利用促進について、貴党はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
障がいの有無にかかわらず平等・公正に行政サービスが提供されることは、国、自治体いずれにおいても当然のことと考えます。情報アクセスをはじめ、さまざまな提供体制を構築し、人材を養成するため、公務員制度などの見直しも含めて取組みを進めることが必要だと考えます。
4.インターネット選挙運動(以下、「ネット選挙」とする)について
4-1)今春の法改正でネット選挙が認められるようになって、初めての国政選挙となります。
これまで、FAXやメールでの選挙運動等は認められなかったことを鑑みると、選挙に関するアクセシビリティとしては大変有効であると考えます。しかし、電話の出来ない聴覚障害者の候補者がFAXやメールで投票依頼をすることは現在も認められておりません。上記について、貴党はどのようなご見解をお持ちですか。
4-2)障害者総合支援法の意思疎通支援事業において、自治体の裁量で、選挙や政治活動への手話通訳および要約筆記の派遣が可能となりましたが、自治体の派遣要綱では派遣を不可とするところが多い現状にあります。上記について、貴党はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
4-1)について
インターネットの使用も含めて、公職選挙法の抜本的な見直しが必要だと考えます。それぞれの市民が行いたい、行えるかたちで自由に選挙運動ができるよう見直し、FAXやメールでの投票依頼も原則として可能とすべきだと考えます。
4-2)について
選挙や政治活動は重要な社会参加のひとつだと考えます。そのことから、手話通訳や要約筆記の派遣については、原則として対象とすべきだと考えます。
5.政見放送への手話通訳・字幕付与の義務化、選挙時の情報保障について
5-1)別紙①の通り、政見放送への手話通訳・字幕付与について、衆議院・参議院共に統一されておりません。
同じ国民でありながら候補者を選ぶ権利、参政権を行使するための情報の入手が制限されている状況を、貴党はどのようにお考えか、見解をお聞かせ下さい。
5-2)また、このたびの選挙において、政見放送、個人演説会、選挙公報など貴党の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?
回答)
5-1)について
障がいの有無に関わらず平等・公正に情報保障されることは、当然のことと考えます。3年ほど前に、総務省で政見放送についてのしくみを見直すための検討の場が、当事者の方々の参加のもとに進められていました。その後、具体的な見直しに至っておらず、早急にその検討、実施すべきだと考えます。
5-2)について
無所属となりました現在、さまざまなハードルはありますが、できるかぎりすべての人に同じ情報が届くよう努力していきます。
6.障害者差別解消法について
本年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が国会に提出されました。障害者差別解消法における、情報アクセスやコミュニケーションの保障への「合理的配慮」、紛争解決にあたる機関の在り方等について、貴党のご見解をお聞かせください。
回答)
「合理的配慮(義務)」については、障害者権利条約にもとづき個別の事案についてその可否が判断されるものであると考えます。そのためには一定のガイドラインなどの提示が必要で、法の施行までにその策定がなされることと思います。その策定過程での当事者・市民の参加が重要であり、その点十分にチェックしていきたいと思います。また、「紛争解決」については、将来的には独立した機関の設置が必要だと考えます。
7.障害者差別解消法について
本年4月、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」(障害者雇用促進法改正法案)が閣議決定、国会に上程されましたが、日本における企業の法定雇用率に対する取組みや、ハローワークにおける手話協力員制度および雇用・労働分野における聴覚障害者専門の相談支援のための職場適応援助者(ジョブコーチ)事業を拡充させるために、貴党のご見解をお聞かせください。
回答)
この間、障害者雇用促進法と障害者差別解消法との関係性などについて、審議会等で検討されてきました。その結果、雇用・就労等における障害者の差別解消については、障害者雇用促進法で進めることとなりました。ハローワークも含めて募集から労働環境まで幅広く、その対策のための取組みが進められることと思います。その動向において、手話協力員制度、相談支援、ジョブコーチ事業等が促進されるよう監視していきます。また、法定雇用率などについては、特例子会社制度等も含めて、検証検討が必要だと考えます。
8.情報・コミュニケーションを保障する法律・制度の必要性について
障害者福祉以外に医療、福祉全般、教育(高等教育含む)、司法、就労、放送・通信など社会のあらゆる分野で障害者の情報アクセスやコミュニケーションを権利として保障する法制度は、すべての障害者の生命や社会参加を保障するという重要性にも関わらず、確立していません。情報アクセシビリティを確立させる為の環境整備(機器・システム・サービスの標準化・規格化、放送・映像への手話通訳および字幕の付与等)を諮るとともに、情報アクセスやコミュニケーションを保障する法制定に向けて、貴党はどのようにお考えか見解をお聞かせください。。
回答)
障害者差別解消法の施行に向けた動向や、当事者の方々の課題などを掘り下げ、情報・コミュニケーション保障のための法律も含めた制度の検討を進めたと考えます。
9.その他
聴覚障害者福祉施策について、貴党が特に取組みたいとされていることをお聞かせください。
回答)
聴覚障害者の方々が日常的に課題とされている事項など、特に制度との関係について具体な事柄を収集し、その克服に向けて参議院議員としての役割を全うしたいと考えています。ぜひ、関係する当事者のみなさんや支援者のみなさんと協力のもとに進めていきたいと思います。
●日本共産党 吉良よし子
<質問事項>
1.障害者総合支援法について
障害者福祉は利用者負担なしで、全国共通の仕組みを作るべきだと思います。この度、成立した障害者総合支援法には「視聴覚障害者の意思疎通支援事業」が含まれましたが、地域間格差や不十分な予算措置等の問題は依然として残ったままです。障害者総合支援法は施行後3年以内に検討事項と附帯決議の具体化を決めています。
今後の障害者総合支援法の見直しや拡充に対するご見解をお聞かせください。
回答)
障害者総合支援法は、障害者の尊厳と生活をふみにじる応益負担を残すなど、「障害者自立支援法」を事実上恒久化したものとなっています。「視聴覚障害者の意思疎通支援事業」が位置づけられたことは重要ですが、ご指摘のような問題点があります。日本共産党は、障害者総合支援法はすみやかに抜本的に見直し、障害者総合福祉法の制定に向けて障害者制度改革推進会議の総合福祉部会がまとめた「骨格提言」にそった真の総合福祉法を制定すべきと考えます。「骨格提言」は、障害者が障害のない人と地域で平等に生活するために必要な支援を確実に保障すること、障害に伴う必要な支援は原則無償とすること、合理性を欠く地域格差は是正されるべきこと、障害程度区分(障害支援区分)の廃止、介護保険優先原則の見直しなど、総合福祉法の基本を示しています。これは、立場の違いを乗り越えて、約1年半をかけて練り上げられた当事者の総意であり、非常に重いものだと考えます。
2.障害者総合支援法における都道府県・市町村等の意思疎通支援事業について
今回、厚生労働省の補助事業として、厚生労働省と全日本ろうあ連盟をはじめとする関係者等で協議を重ね、意思疎通支援者の派遣に係るモデル要綱およびガイドラインを作成しました。
しかし、「手話通訳設置事業」については、すでに多くの都道府県が行っているにもかかわらず、都道府県の必須事業とはなりませんでした。
また、設置される手話通訳者の身分、労働条件等が市町村によって異なっている状況です。
その現状と照らし合わせ、施行後3年以内の見直し検討に向けて、手話通訳者および要約筆記者の養成・認定事業や設置事業、そして盲ろう者通訳・介助者の養成、派遣事業のモデル要綱およびガイドラインを作成していく必要があります。これについて、貴党のご見解をお聞かせください。
回答)
総合支援法では、「意思疎通支援事業」が位置付けられましたが、自治体主体である地域生活支援事業とされ、とりくみや手話通訳者の労働条件などについて、自治体間の格差が生まれていることは問題です。身体障害者手帳をもたない聴覚障害者も含め、どの自治体に住んでいても誰もが手話通訳者や要約筆記者の派遣を受けられるようにすべきです。「骨格提言」は、「コミュニケーション支援及び通訳・介助支援」を「全国共通の仕組みで提供される支援」と位置付けており、総合支援法の抜本見直しにあたっては、「意思疎通支援事業」を国の事業とするべきと考えます。また、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳・介助者などの高い専門性に見合った報酬・労働条件の保障は当然です。手話通訳設置事業を必須化し、要約筆記者の要請・認定事業や設置事業、盲ろう者通訳・介助者の養成、派遣事業のモデル要綱およびガイドラインの作成を求めていきます。
3.行政サービスのアクセシブルな利用について
身体障害者手帳を持たない聴覚障害者、聴覚に障害のある者と意思疎通の必要のある者など、誰もが自由に利用できる制度には至っておりません。また、聴覚障害者が自分の希望するコミュニケーション手段を使ってのサービス提供を受けるに至っていない現状があります。
国民である以上、障害の有無にかかわらず行政のサービスを受けられるべきであり、それを提供する義務が行政機関にはあると考えます。
例えば、情報アクセスのバリア解消のため、都道府県市町村の福祉事務所等に手話で相談できるケースワーカー等の相談員の配置や地方自治体の窓口における筆談対応の職員研修、手話のできる職員の配置等を推進する必要があります。
行政機関のアクセシブルな利用促進について、貴党はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
ご指摘のとおり、障害があるゆえに行政のサービスを十分に受けられない状況があってはなりません。障害がある人もない人も、等しく行政のサービスが受けられることは、国民の権利であり、それを保障するのは行政の重要な責任です。日本共産党は、これまでも、行政窓口などに手話や筆談対応ができる職員を配置することなど、アクセシブルな情報提供の推進にとりくんできました。また、交通機関や道路、投票所、銀行などのバリアフリー化にも力をつくしてきました。今後も、国に対し、地方任せにするのでなく、アクセシブルな利用の保障をすすめようつよめていきます。
4.インターネット選挙運動(以下、「ネット選挙」とする)について
4-1)今春の法改正でネット選挙が認められるようになって、初めての国政選挙となります。
これまで、FAXやメールでの選挙運動等は認められなかったことを鑑みると、選挙に関するアクセシビリティとしては大変有効であると考えます。しかし、電話の出来ない聴覚障害者の候補者がFAXやメールで投票依頼をすることは現在も認められておりません。上記について、貴党はどのようなご見解をお持ちですか。
4-2)障害者総合支援法の意思疎通支援事業において、自治体の裁量で、選挙や政治活動への手話通訳および要約筆記の派遣が可能となりましたが、自治体の派遣要綱では派遣を不可とするところが多い現状にあります。上記について、貴党はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
4-1)について
ご指摘の点は、たいへん矛盾があり問題だと考えます。FAXやメールでの働きかけを認めるべきです。
4-2)について
ご指摘のような状況があることはたいへん残念であり問題です。国は、手話通訳および要約筆記の派遣が可能であることをあらためて周知徹底し、自治体の派遣要綱に定めることを促進すべきです。
5.政見放送への手話通訳・字幕付与の義務化、選挙時の情報保障について
5-1)別紙①の通り、政見放送への手話通訳・字幕付与について、衆議院・参議院共に統一されておりません。
同じ国民でありながら候補者を選ぶ権利、参政権を行使するための情報の入手が制限されている状況を、貴党はどのようにお考えか、見解をお聞かせ下さい。
5-2)また、このたびの選挙において、政見放送、個人演説会、選挙公報など貴党の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?
回答)
5-1)について
参政権の保障は、憲法が定める国民主権、議会制民主主義の原則を実現するために必要不可欠なものであり、基本的人権にかかわる問題です。障害があることで、参政権を行使するための情報が十分に入手できないということは憲法に違反する事態であり、あってはなりません。日本共産党は、こうした立場から、点字や声の政策の発行、演説会における手話通訳や盲ろう者向け通訳の配置など政党自身でできる対応をすすめるとともに、政見放送への手話や字幕の義務づけ、点字や声の選挙広報の発行、在宅投票制度の拡充、投票所のバリアフリー化などをいっかんして求めてきました。今後も障害者の参政権の保障について、いっそう努力をつよめたいと考えます。
5-2)について
都内で行う各種の演説会では、手話通訳の配置や磁気ループの活用、要約筆記、盲ろう者向けの通訳・介助の実施などに努めていきたいと考えます。また、日本共産党の政見放送においては手話通訳を行っています。
6.障害者差別解消法について
本年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が国会に提出されました。障害者差別解消法における、情報アクセスやコミュニケーションの保障への「合理的配慮」、紛争解決にあたる機関の在り方等について、貴党のご見解をお聞かせください。
回答)
「障害を理由とする差別の解消を推進」すると明記した障害者差別解消法の成立は、障害者の差別解消にむけた重要な一歩ですが、同法制定に向けて設置された差別禁止部会の「意見」の水準と比較しても、「差別」の定義がないなど多くの課題があります。同法は、「合理的配慮の不提供」を禁止しますが、国の行政機関や地方公共団体等には法的義務を課す一方、民間事業者には努力義務を求めるのにとどまっています。何が差別に当たるのか、合理的配慮の具体的内容などは、今後作成されるガイドラインに委ねられており、障害者権利条約の趣旨に適合するガイドラインとなるよう求めていきます。「合理的配慮」の中に、行政機関の義務としての情報アクセスやコミュニケーション保障が含まれるべきなのは当然です。また、同法は、紛争解決の救済機関は既存の機関等を活用するとしていますが、差別禁止部会の「意見」は紛争解決の仕組みとして相談や調整などを行う第三者機関の設置を提案していました。実効性ある権利救済のためには、政府から独立した第三者機関が必要だと考えます。
7.障害者差別解消法について
本年4月、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」(障害者雇用促進法改正法案)が閣議決定、国会に上程されましたが、日本における企業の法定雇用率に対する取組みや、ハローワークにおける手話協力員制度および雇用・労働分野における聴覚障害者専門の相談支援のための職場適応援助者(ジョブコーチ)事業を拡充させるために、貴党のご見解をお聞かせください。
回答)
法定雇用率が毎年未達成であることは非常に問題です。民間事業者は努力義務ではなく義務化し、とくに大企業に法定雇用率を遵守するようにすべきだと考えます。また、中小企業には助成金を増額するなどの支援を行うべきです。ハローワークにおける手話協力員制度、聴覚障害者専門のジョブコーチ事業を拡充させるため、十分な予算の確保を求めます。
8.情報・コミュニケーションを保障する法律・制度の必要性について
障害者福祉以外に医療、福祉全般、教育(高等教育含む)、司法、就労、放送・通信など社会のあらゆる分野で障害者の情報アクセスやコミュニケーションを権利として保障する法制度は、すべての障害者の生命や社会参加を保障するという重要性にも関わらず、確立していません。情報アクセシビリティを確立させる為の環境整備(機器・システム・サービスの標準化・規格化、放送・映像への手話通訳および字幕の付与等)を諮るとともに、情報アクセスやコミュニケーションを保障する法制定に向けて、貴党はどのようにお考えか見解をお聞かせください。。
回答)
障害者や高齢者にやさしい社会は、すべてに人々にとってもやさしい社会です。情報アクセスやコミュニケーションを保障する法制定は当然必要であり、実現をめざしてとりくんでいきたいと思います。
9.その他
聴覚障害者福祉施策について、貴党が特に取組みたいとされていることをお聞かせください。
回答)
障害者総合支援法を抜本的に見直し、「基本合意」「骨格提言」にもとづいた障害者総合福祉法を制定します。応益負担は廃止し、障害者の福祉・医療を無料にします。地域生活支援事業の予算を大幅に拡充し、利用料やメニューの地位間格差をなくします。移動し円、意思疎通支援事業等の利用料を無料化し、国の制度として位置づけます。必要とする全ての人が手話通訳や要約筆記の派遣を受けられるように施策拡充をすすめます。高い専門性に見合った手話通訳者やコーディネーターの身分保障を求めます。都政では、日本共産党都議団と協力し、1996年に月1万5500円になったまま、17年連続して1円もあがっていない都の心身障害者福祉手当の増額をはじめ、障害者福祉の利用者負担軽減など経済的支援の拡充強化、手話通訳者、要約筆記者養成事業の拡充、講師単価や会場費の増額、聴覚障害者に対する大規模災害時の支援体制の強化、聴覚障害者向け火災警報器の設置購入助成の実施、および都有施設への設置促進などをすすめます。党都議団が昨年9月に発表した、「難聴者支援に関する東京都への提言」の全面実現をすすめます。障害者手帳を持たない中等度難聴児の補聴器購入費支援は、今年度新規事業で実現しました。「聞こえの相談体制」整備、「聞こえのバリアフリー」の推進、高齢者に対する補聴器購入費助成、磁気ループの普及などの実現をひきつづき求めていきます。